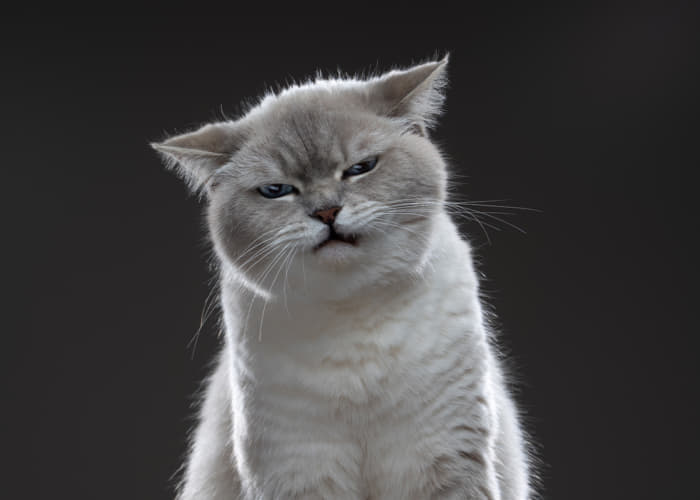冬の猫あるある!猫との嬉しい冬生活/もちもちブラザーズコラム

こんにちは、11匹の猫と暮らすニャンスタグラマーのmochi_ryokoです。
今回は、猫を飼っている家庭ではお馴染みの「冬の猫あるある」を紹介していきたいと思います。
猫を飼っている人ならきっと「あーわかる!」と共感してくれるはず!
まだまだ寒い時期が続きますが、この記事を読んでほっこりしてもらえたら嬉しいです♪
お布団に猫がやってくる!

寒くなってくると、夜寝る時にお布団に猫が入ってきます!
冬毛でフワフワモコモコ、喉をゴロゴロ鳴らしている猫を腕枕しながら寝る…こんな幸せがあるでしょうか?
猫飼いにとって、お布団に猫が入ってくるのは、冬の醍醐味と言っても過言ではありません。
しかし、そんな幸せも朝には打ち砕かれるのです。
「あれ?なんか体が痛い…」しっかり寝たはずなのに体が痛い!これぞ冬の猫あるあるでしょう!
添い寝の代償
猫と添い寝すると、無意識で猫に遠慮して寝ることになります。
そのため、変な体勢で長時間動けなかったりするので、休ませたはずの体が逆にバキバキになっていることも!
うちの場合だと、左腕にきなこ・右腕によもぎ・股の間におはぎという布陣になるので、朝起きると腕と腰が痛いです。
しかもたまにきなこが首の上に乗って寝ていることがあり、息苦しさで起きることもあります。
しかし、8匹の猫と同じ部屋で寝ている母はもっと大変でした。
私と同じように左右に猫、そして布団の上に3、4匹の猫団子が重りのように乗っかっているというのです。
1匹とかなら布団を動かすこともできますが、数匹乗っていると布団はびくともしないようで、寒くて目が覚めることもあるんだそう。
添い寝は幸せですが、こんなつらい代償もあるんですね…(汗)
暖房器具の奪い合い

ストーブやこたつはいつも猫と人間の奪い合いです。
もちもちブラザーズの部屋にはこたつがあるのですが、基本的に人間が入る隙間はありません(笑)
こたつにはよもぎ・きなこ・おはぎがむぎゅむぎゅに入っています。
足を入れようとすると、よもぎの猫パンチ&ガブガブを受けるか、きなこおはぎに足をロックされて身動きが取れなくなって足が痺れるかの2択です。
また、ストーブの前もいつも猫で混雑しています。
ストーブの前で数匹が猫団子になっている姿はとても可愛いのですが、私もストーブにあたりたいです…(笑)
部屋が寒い

我が家はいくつかの部屋を猫に開放しているので、猫たちは自分の好きな時に好きなように移動します。
そのため、部屋のドアは常時、猫が通れるくらいの隙間を開けている状態です。夏はそれでも良いのですが、冬は隙間風が寒い!
しかし、寒いからといってドアを締め切っていると、ドアの外から「にゃーん!(中にいれてくれー!)」といって鳴いたり、外に出たいといって壁紙をビリビリ破られたりと色々と大変です。
というわけで寒くてもそこは我慢しなければならないのです。
※猫ドア設置しようか真剣に悩んでいますが、おデブな子もいるのでどうなんだろう?という感じです
静電気パチパチ

冬の猫は冬毛でフワッフワ!しかし、猫を撫でようとするとパチッと静電気が…なんて経験ありませんか?
ただでさえニットなどの冬物の洋服は静電気が起きやすい上に、空気が乾燥しているので、なかなか避けることができません。
猫がせっかくご機嫌で近寄ってきて愛情表現をしてくれようとしているのに、静電気のせいで不機嫌になって逃げていくこともありますよね。
お鼻チューしようとして指から静電気が走ったら、「なにするの?ひどい!」みたいな顔されます。
「違うんだよー!」って思わず言いたくなりますが、静電気は猫にも人間にも不快なものなので、できるだけ対策したいところ。
猫を触る前に壁にタッチしたりして放電すると良いらしいです。
と、わかっていてもついつい忘れてパチッっとやってしまうものです…
■あわせて読みたい記事■
冬の猫との暮らしは幸せいっぱい
冬の猫あるあるを紹介しました♪
普段ツンデレな猫たちも、冬になるとぴったりひっついてきて幸せな気持ちになりますよね。
いつもより距離が縮まって、猫ちゃんとの信頼関係もますます強くなります。
布団やストーブを取られたりして大変なこともありますが、これも冬の風物詩だと思って楽しんでくださいね。
mochi_ryoko
出典:@mochi_ryoko
出典:@mochi_ryoko
<PROFILE>
2020年3月に東京から実家のある山口県へ3匹の猫「もちもちブラザーズ」こと、よもぎ♀・きなこ♂・おはぎ♂と共に移住。実家の先住猫7匹と「もちもちブラザーズ」合わせて10匹の猫との新生活を始める。さらにその後、2020年7月に自宅へ迷い込んできた子猫を保護し、現在は11匹の猫とドタバタ生活を送っている。Instagramは4万人以上のフォロワーがいる大人気ニャンスタグラマー。
Instagram:@mochi_ryoko