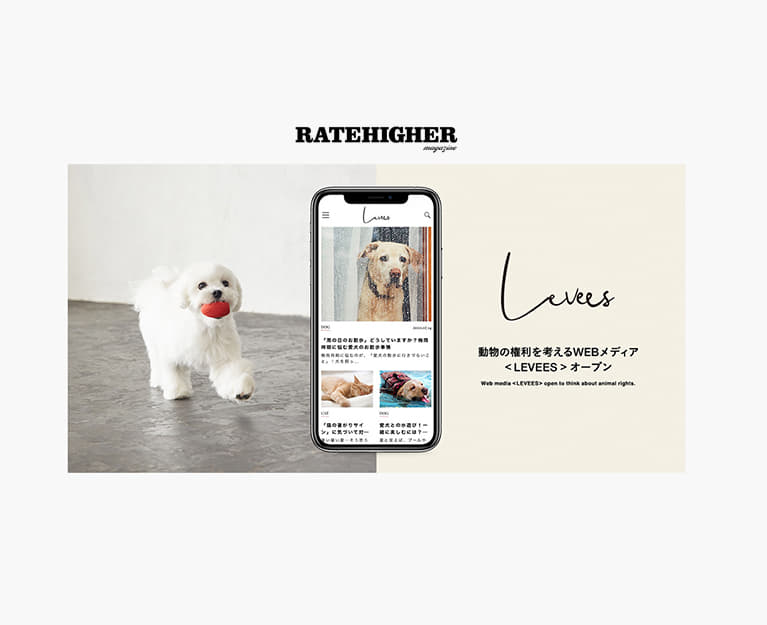これからペットを飼おうとしている方へ、ぜひ読んで欲しい記事です。

物々しいタイトルとなってしまいすみません。
これからお届けするのは、ペットを飼いたいと思っている方へ読んで欲しい記事です。
ペットを飼おうか迷っている方。迷った末に飼おうと決めた方。将来いつか飼いたいと考えている方。実際に飼う前に、ぜひとも読んでいただければ幸いです。ひとり残らず幸せに暮らして欲しい。
日頃笑顔をくれる動物たちにそう願っている1人として、大切に綴っていきます。
あなたの「飼いたい理由」はなんですか?

ペットと言っても様々ですが、どんな動物と一緒に暮らしたいと考えていますか?
犬、猫、うさぎ、鳥、爬虫類、亀など。
日本でペットとして認められている動物はたくさんいます。
特徴や育て方など、それぞれ異なりますが、共通していることは「生きている」ということです。
つまり、「ペットを飼う」ということは「一緒に暮らしていく」ということ。
責任をもって最後までお世話をしなくてはいけません。
だからこそ飼いたい理由が、「かわいいから」「飼ってみたいから」「ひとりで寂しいから」など一時的な感情に任せたものになると、飼い主さんも一緒に暮らす動物も、悲しくつらい想いをする可能性があるのです。
今一度自分自身に問いかけてください。
「ペットを飼いたい理由はなんですか?」
「生涯その子の面倒をみていけますか?」
ペットにとって「あなた」は唯一の友達であり家族であり味方です

「あなたにはあなたの仕事や楽しみもあり、友達だっているでしょう。
でも、私にとってはあなたがすべてなのです」
世界的にも有名な「犬の十戒」という詩の一節です。
この詩通り、ペットにとってはあなたが全て。
あなたには楽しく遊んでいる時間も、お酒を飲んでいる時間も、お仕事をしている時間もあるでしょう。
でも、ペットにとっては「あなたとの時間」が全て。
しっかりと一緒に過ごせる時間はあるのか考えて、ペットを飼うか判断してください。
そしてもしもまだ犬の十戒を読んだことのない方は、ぜひとも目を通してみてくださいね。
ペットの気持ちに少しでも寄り添うことが出来るはずですよ。
■あわせて読みたい記事■
「もしも」の場合を考えていますか?

もしも、あなたが病気や怪我で入院しなくてはいけなくなったら。
もしも、お仕事で今よりもうんと多忙になったら。
もしも、引越しをしなくてはいけなくなったら。
もしも、動物のアレルギー反応が出てしまったら。
もしも、生活環境が大きく変わってしまったら。
あなたはそれでもペットを最後までお世話することができますか?
もちろん病気や怪我など、防ぎようのないどうしようもない理由もあります。
しかしその場合でも、代わりにお世話が出来る人は身近にいますか?
「飼えなくなったから、里親に出す」
「お世話が大変だから、保護団体へ預ける」
「想像と違ったから、手放す」
そんな理由で唯一の味方と離れ離れになる動物のこと、考えてあげてください。
「飼えないのかもしれない」のなら「飼わない」。
「自信や責任がない」のなら「飼わない」。
それもまた、動物に対する愛なのだと思っています。
たくさんの幸せを運んでくれる存在

厳しいことばかりを書き連ねていきましたが、ペットを飼いたい気持ちを否定したいわけではありません。
ただ、相当の決意や想いが必要になる、とお伝えしたかったのです。
動物は本当にたくさんの幸せを運んでくれます。
元気がない時は、笑顔にしてくれて。
悲しい時は、そっと寄り添ってくれて。
落ち込んだ時には、可愛い仕草で笑わせてくれて。
振り返ってみると私自身、小さい頃からペットに支えられた人生だったと思います。
でも、だからこそ。
軽い気持ちで、ペットを家族として迎えて欲しくない。
人も、動物も、一緒に幸せに暮らすために。
飼いたいと思っている方は、今一度真剣に考えてご検討いただけたら嬉しいです。
ペットとの暮らしは、本当に幸せなもの。
自分の人生が今よりも少し、愛おしくなります。
もしも飼いたいと思ったら、譲渡会や里親募集の情報を探してみてください。
きっと最高のパートナーと出逢えるはずですよ。